はじめに
賃貸マンション経営をしていると、「家賃収入はあるのに、税金が高くて思ったより手元に残らない……」と感じることはありませんか?
本記事は、賃貸経営を行う個人オーナーや副業で不動産投資をしている方に向けて、所得税の仕組みと節税対策について分かりやすく解説します。
「どんな税金がかかるの?」「どうすれば節税できる?」といった疑問を持つ方に役立つ内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
1. 賃貸マンション経営にかかる税金の種類
賃貸マンション経営を始めると、さまざまな税金を支払う必要があります。これを理解せずに経営を続けると、思わぬ税負担に驚くことになります。
例えば、「家賃収入が増えたのに手元にお金が残らない!」と感じたことはありませんか?これは、税金の計算方法を把握していないことが原因かもしれません。
ここでは、賃貸経営に関わる主な税金について説明します。
1-1. 所得税
所得税は、賃貸経営による利益(不動産所得)に対して課されます。サラリーマンで副業として賃貸経営を行っている方も、本業の給与所得と合算して課税されるため注意が必要です。
たとえば、Aさんは会社員として年収600万円を得ています。副業で賃貸マンションを1棟所有し、年間の家賃収入は500万円。しかし、ローンの返済や管理費、固定資産税などの経費を差し引くと、不動産所得は100万円になりました。
この100万円が給与所得600万円に加算され、課税対象の所得が増えることで、結果的に所得税の負担が増えることになります。
1-2. 住民税
住民税は、所得に応じて自治体に納める税金です。給与所得に加えて不動産所得が増えると、住民税の額も上がるため、予め想定しておくことが重要です。
1-3. 個人事業税
事業的規模(一般的に10室以上の賃貸物件)で賃貸経営を行う場合、個人事業税が課されることがあります。これを知らずにいると、後から予想外の請求が来ることも。
1-4. 消費税
賃貸経営では、住居用の家賃収入には消費税がかかりませんが、駐車場や事務所として貸し出す場合には消費税が発生します。
たとえば、Bさんはアパートの1階をテナントとして貸し出し、年間120万円の賃料収入を得ています。この場合、消費税が課税されるため、Bさんは消費税を納める義務が発生します。
2. 所得税の計算方法
2-1. 不動産所得の算出方法
不動産所得は次の計算式で求められます。
不動産所得 = 総収入金額 - 必要経費
たとえば、
-
家賃収入:500万円
-
必要経費:300万円(詳細は下記)
この場合、不動産所得は 500万円 – 300万円 = 200万円 となります。
2-2. 必要経費の内訳
必要経費として認められる主な費用は以下の通りです。
-
固定資産税:所有する賃貸物件に対して毎年課される税金
-
修繕費:設備の修理や補修にかかる費用(ただし、大規模なリフォームは減価償却)
-
管理費・管理委託費:管理会社に支払う手数料や共用部分の維持費
-
ローン利息:物件購入時のローンにかかる利息部分(元本は対象外)
-
減価償却費:建物や設備の購入費用を耐用年数に応じて分割計上
-
火災保険料:物件にかける保険料
-
水道光熱費:共用部分の電気・水道料金
-
広告宣伝費:入居者募集のための広告費用
-
交通費:物件管理のための移動費
-
修繕積立金:将来の修繕のための積立金(管理組合に支払うもの)
これらの経費を適切に計上することで、不動産所得を抑え、所得税の負担を軽減できます。
2-3. 所得税額の計算
この200万円が他の所得と合算され、税率が適用されて所得税額が決まります。税率は所得額によって異なるため、年間の総所得を把握することが重要です。
【所得税率の早見表】
| 課税所得額(万円) | 税率(%) | 控除額(万円) |
|---|---|---|
| 195以下 | 5 | 0 |
| 195~330 | 10 | 9.75 |
| 330~695 | 20 | 42.75 |
| 695~900 | 23 | 63.6 |
| 900~1,800 | 33 | 153.6 |
| 1,800~4,000 | 40 | 279.6 |
| 4,000超 | 45 | 479.6 |
例えば、総課税所得が500万円の場合、税率20%が適用され、控除額42.75万円を差し引いた所得税額は次のように計算されます。
500万円 × 20% - 42.75万円 = 57.25万円このように早見表を活用することで、大まかな所得税額を計算することができます。
この200万円が他の所得と合算され、税率が適用されて所得税額が決まります。税率は所得額によって異なるため、年間の総所得を把握することが重要です。
3. 節税対策のポイント
3-1. 青色申告の活用
青色申告をすると、最大65万円の特別控除を受けることができます。さらに、家族を従業員として給与を支払い、経費として計上することも可能です。
たとえば、Cさんは専業主婦の妻を青色専従者として雇用し、年間100万円の給与を支払っています。この金額は経費として認められるため、課税所得を抑えることができます。
3-2. 減価償却の適用
建物の取得費用を長期間にわたって経費化できる減価償却を活用すると、毎年の税負担を分散できます。
【建物の構造別 耐用年数早見表】
| 建物の構造 | 耐用年数(年) |
|---|---|
| 木造 | 22 |
| 軽量鉄骨(骨格材の厚み3mm以下) | 19 |
| 軽量鉄骨(骨格材の厚み3mm超~4mm以下) | 27 |
| 重量鉄骨(骨格材の厚み4mm超) | 34 |
| 鉄筋コンクリート造(RC造) | 47 |
例えば、Dさんは築20年の木造アパート(購入価格2,000万円)を取得しました。耐用年数22年で減価償却を行うと、年間約90万円を経費として計上できます。
また、既に築年数が経過した中古物件の場合、法定耐用年数の短縮計算が可能になるケースもあります。
建物の取得費用を長期間にわたって経費化できる減価償却を活用すると、毎年の税負担を分散できます。
たとえば、Dさんは築20年の木造アパート(購入価格2,000万円)を取得しました。耐用年数22年で減価償却を行うと、年間約90万円を経費として計上できます。
4. まとめ
賃貸マンション経営では、さまざまな税金が関わるため、適切な節税対策を行うことで手元に残るお金を増やすことが可能です。
特に、
-
青色申告を活用する
-
減価償却費を適切に計上する
-
経費を漏れなく計上する
といった対策を実践することで、税負担を軽減できます。
税務の専門家と相談しながら、賢い賃貸経営を行いましょう!




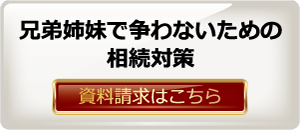
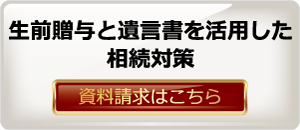
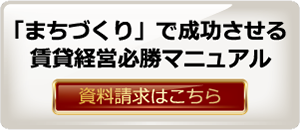
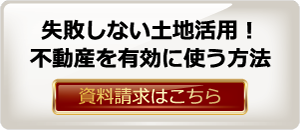




 賃貸マンション経営における所得税の基本と節税対策:成功するためのポイント
賃貸マンション経営における所得税の基本と節税対策:成功するためのポイント