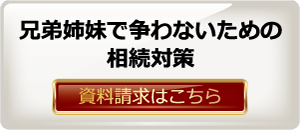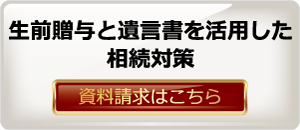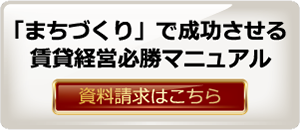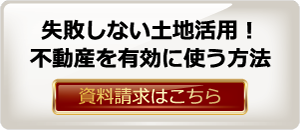はじめに 賃貸マンション経営をしていると、「家賃収入はあるのに、税金が高くて思ったより手元に残らない……」と感じることはありませんか? 本記事は、賃貸経営を行う個人オーナーや副業で不動産投資をしている方に向けて、所得税の仕組みと節税対策について分かりやすく解説します。 「どんな税金がかかるの?」「どうすれば節税できる?」といった疑問を持つ方に役立つ内容となっていますので、ぜひ最後までご覧くだ……
-
TEL.072-250-8808
-
FAX.072-252-1079
 税務blogの記事一覧
税務blogの記事一覧
修繕費と資本的支出の違いとは?税金対策の要点をわかりやすく解説
賃貸マンション経営を行ううえで、建物の維持・管理にかかる費用について正しい知識を持つことは非常に重要です。その中でも「修繕費」と「資本的支出」の違いを理解することで、適切な経費計上が可能となり、結果的に税負担を大幅に軽減できます。本コラムではそれぞれの定義、具体例、税務上のポイントについて詳しく解説します。 修繕費とは? 修繕費の定義 修繕費とは、資産を元の状態に回復させるためにかかる費……
減価償却の活用術:賃貸マンションの節税メリットを最大化する方法
減価償却とは、建物や設備などの資産が経年劣化や使用によって価値を減少させることを前提に、その減少分を一定期間にわたり経費として計上する仕組みです。賃貸経営において減価償却を正しく活用することで、所得税負担を軽減する効果が期待できます。 賃貸経営では収入に対する税負担が大きな課題です。減価償却費は現金の支出を伴わずに経費計上できるため、利益圧縮を通じて節税効果をもたらします。その結果、健全な資金繰……
借地を相続することはできるのですか?
借地とは、土地を貸していると地主さんとその土地を借りている借地人という相互の関係があって成り立つものです。 今回は土地を借りている人(借地人)からその土地を相続をするときの流れで浮かび上がる疑問について調べてみました。 地主さんとの契約の確認は必要でしょうか? 借りている土地(借地)を相続するために、地主さんとの契約を確認すべきなのか?ということは多くの方が持つ疑問です。……
遺言控除創設と消費税に軽減税率
財務省が提案した日本型軽減税率は廃案のようです。 年末に向けてこの課題を中心に議論されるようです。 経済産業省からは「役員給与の損金算入範囲の見直し」「取引相場のない株式の評価方式の見直し」など、金融庁からは「上場株式等の相続税評価の見直し」など、農林水産省からは「農地を中間管理機構に貸し付けた場合の固定資産税の免除」などそれぞれ気になる改正要望が出ています。 自民党の「家族の絆……
産業競争力強化法案について
この税制改正は製造業だけではなくすべての業種が対象となります。 ただ、どのような設備でも対象となるのではなく、生産性が年平均1%以上向上する一定の設備や建物の改修、電気設備や冷暖房設備、昇降機設備、ブラインドなどが対象となります。 注意しなければならないのは、この法律の施行日以後に取得したものから適用することとされているので、早く買いすぎると一括して全額費用化で……
相続税の税務調査ってどんなもの?
相続税にも税務調査があるのをご存知でしょうか。しかも、それはいつ頃来るのか? 来たらどうしたらいいのか?など心の準備があるのとないのでは大きく違いますね。 「うちは財産が少ないから大丈夫!」と思っていたら・・万が一ということもあります。 ここでは来るべき相続税の税務調査が来た時についての対処、お役立ち情報を先取りでお伝えします。 &nbs……
任意後見人とは?
任意後見人は今後高齢者が増える世の中でますますニーズとしては重要になってきます。 認知症などで何もわからない場合、任意後見人の働きが大きく影響します。 その仕組みを理解してみましょう。 任意後見の仕組みとは? 今後の認知症高齢者の増加は高齢化社会に伴い、かなりの率に上がっています。 内閣府によれば平成24(2012)年は、462万人と65歳以上の7人に1人……
結婚・子育て資金の贈与は、相続対策として活用できるのか?
結婚・子育て資金の贈与は、相続対策として活用できるのか 平成26年12月30日に、自民党・公明党の税制改正大綱が示されました。 そのなかに、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税枠創設が記載されています。 これまでの教育資金の贈与にプラスして結婚・子育てに係る一定の資金の贈与についても非課税になる制度です。 いま、日本で富裕層と言われている……
相続放棄
相続放棄とは、家庭裁判所に相続放棄の申述をして受理されることを言います。 まず、ここが一般的に言われる相続放棄と、法律上の相続放棄の大きな違いです。 この時に裁判所に交付を依頼して発行される「相続放棄申述受理証明書」があれば、最初から「相続人でなかった」ことになりプラスの財産も借金(マイナスの財産)も引き継ぎません。 そうなると、今まで相続人でなかった人(祖父母やお……